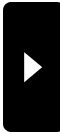2014年03月15日
Posted by こち at
2014年03月15日01:21 Comment(0)
高尾山の石組遺構
観音寺市大野原町の高尾山。496m
豊稔池の北側の山である。
豊稔池よりさらに西に進んだ田野々地区から上がっていく。
最初は未舗装のフラットな林道を快適に進む。

この後は、イノシシの掘り返した跡と石が散乱していて足場は悪くなってくる。
小さな峰を登り降りすると、ほぼ崖のような斜面にあたり這うように登って行く。
するとこのピークのてっぺんに、立派な石組みが見えてくる。
二段の石垣で組まれた台座に乗る社である。

かなり古いもので掘られた字は読みづらいが、寛永とだけみえるので江戸時代の物らしい。

高尾山の頂上はさらに東へ進まないといけない。
この散乱した石、どうやらこの峰の自然石を割って配置していたものらしい。

石畳、もしくは石段が往時は完備した立派な道だったようである。

石組みで作られた排水溝らしき遺構も見える。
尾根筋をしばらく進むとまた峰がある。
この峰は完全な石段、もしくは城壁状になっている。

峰のてっぺんには、磐座らしき巨石も積まれている。ここからは見晴らしがよく、伊吹島や観音寺の平野まで見渡せる。
通信施設の設置には最適である。

さらに東へ峰を下るが、その尾根筋はやはり石畳が敷かれていたらしく、手ごろな大きさの割石が無数に地表に顔を出している。
頂上の登りも石段であったらしく、途中小さな立石もある。

頂上にはとりたてては何もないが、さらに進んだ東側の斜面も石段であったようだ。

頂上の峰を降り切ると石は突然無くなってしまう。
その後一つ峰を進んだが、全く石は転がっていないので、西の端の社から頂上の峰までが、何らかの遺跡であるのは間違いない。

超古代の通信施設跡かもしれないし、屋島とならぶ古代城郭であったかもしれない。神社かお寺になったのはその後であろうとは思うが、長い歴史の中、誰かが何かのためにおそらく何度も、違う目的のために築いたのであろう石組みがこうして放置されているのを見ると残念である。
幸いこの付近の山の尾根筋はどこも防火帯として、定期的に草刈が行われているので、ほかのほったらかしの山に比べると保存がよい。
確実なのは、ここは寛永年間以前に建てられた神社があることである。少なくとも400年ぐらい前から続いていることだけは確かだ。
※写真中、自転車が多数写っていますが、まず乗って行けるところではないので参考にはなさらない方がミノタメかと。
より大きな地図で 磐座 を表示
豊稔池の北側の山である。
豊稔池よりさらに西に進んだ田野々地区から上がっていく。
最初は未舗装のフラットな林道を快適に進む。
この後は、イノシシの掘り返した跡と石が散乱していて足場は悪くなってくる。
小さな峰を登り降りすると、ほぼ崖のような斜面にあたり這うように登って行く。
するとこのピークのてっぺんに、立派な石組みが見えてくる。
二段の石垣で組まれた台座に乗る社である。
かなり古いもので掘られた字は読みづらいが、寛永とだけみえるので江戸時代の物らしい。
高尾山の頂上はさらに東へ進まないといけない。
この散乱した石、どうやらこの峰の自然石を割って配置していたものらしい。
石畳、もしくは石段が往時は完備した立派な道だったようである。
石組みで作られた排水溝らしき遺構も見える。
尾根筋をしばらく進むとまた峰がある。
この峰は完全な石段、もしくは城壁状になっている。
峰のてっぺんには、磐座らしき巨石も積まれている。ここからは見晴らしがよく、伊吹島や観音寺の平野まで見渡せる。
通信施設の設置には最適である。
さらに東へ峰を下るが、その尾根筋はやはり石畳が敷かれていたらしく、手ごろな大きさの割石が無数に地表に顔を出している。
頂上の登りも石段であったらしく、途中小さな立石もある。
頂上にはとりたてては何もないが、さらに進んだ東側の斜面も石段であったようだ。
頂上の峰を降り切ると石は突然無くなってしまう。
その後一つ峰を進んだが、全く石は転がっていないので、西の端の社から頂上の峰までが、何らかの遺跡であるのは間違いない。
超古代の通信施設跡かもしれないし、屋島とならぶ古代城郭であったかもしれない。神社かお寺になったのはその後であろうとは思うが、長い歴史の中、誰かが何かのためにおそらく何度も、違う目的のために築いたのであろう石組みがこうして放置されているのを見ると残念である。
幸いこの付近の山の尾根筋はどこも防火帯として、定期的に草刈が行われているので、ほかのほったらかしの山に比べると保存がよい。
確実なのは、ここは寛永年間以前に建てられた神社があることである。少なくとも400年ぐらい前から続いていることだけは確かだ。
※写真中、自転車が多数写っていますが、まず乗って行けるところではないので参考にはなさらない方がミノタメかと。
より大きな地図で 磐座 を表示