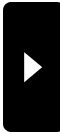2016年01月14日
Posted by こち at
2016年01月14日14:58 Comment(0)
保久良神社磐座
保久良神社は 、兵庫県芦屋市にある神社である。
地元の人以外でし知っているのは 、六甲山を登る人か、カタカムナ文字に興味のあるマニアくらいでしょう。
その昔この神社のある金鳥山山中で楢崎皐月が平十字なる人物よりのカタカムナ文字の巻物を見せられたという 。ただそのカタカムナ文字は、保久良神社とは直接の関係は無いようで、神社の記述にはどこにも見られない。
そもそも真偽すら明らかでない文字なので、本当に金鳥山で見せられたのかも怪しい。平十字という名前も金鳥山西側にある十文字山からとってるんじゃないかとも思われる。
私はカタカムナ自体を疑っているのではなくて、その場所を楢崎氏がぼかしているんじゃないのかと思っている。
以前読んだ本では、「池の周りに調査のために張ったワイヤーが動物の生活に影響を与えていると言って、平十字と名乗る猟師がクレームをつけてきて云々」と書かれていたと記憶しているが、金鳥山には池が見当たらないのである。
どこか別の山で起こった出来事を金鳥山に置き換えている、もしくは近辺の山の総称として金鳥山といったのかもしれない。
それはともかく、この保久良神社、磐座の宝庫である。

今回、高松深夜1時発のフェリーで神戸に5時過ぎに着き、そのまま保久良神社へ向かったので到着時、真っ暗である。
この時間に金鳥山を登るのは無謀かもしれないと思いつつ、近くのコインパーキングに車を停め、保久良神社に向かう。
神社に近付くにつれ、5時半だというのに何人もの人とすれ違ったり、追い越したりする。
境内に着くとこの時間のこんぴらさんではまず見られないほどの人が参拝している。
ただ、拝殿の前以外は暗くて何も見えないので、参拝だけすませて登山道へ向かう。
ただ、初めての場所なので、道の分岐点が見えないし、わからない。
他の人達が歩いて行く方へついて行くと、登山道の道標があった。
念のためにと持ってきていたヘッドランプと光量の強い懐中電灯を頼りに、出発。
大阪湾の夜景がきれいです。
さすがに大部分の人は参拝だけで、登山道にはほとんどいない。
ライトの灯りと自分の足音以外何もきこえない暗闇の中で、突然物音が、イノシシかと思いきや、他の登山者の足音。
他にも登っている人がいてひと安心、結局往復で20人以上に会いました。
田舎では昼間でもそんなに多くの人に会うことは無いので、びっくりです。
で、金鳥山の登山道にはほとんど石らしいものがなかったので、さらに進んで風吹岩という見晴らしのいいところへ。

ほとんどの石が切ったように角があり、単に風化して地上に現れたものでは無いような気もするが、今のところ特に祭祀していたとかという情報は聞いたことが無い。


メンヒルか磐座だと思うんですが。
猫がいました。ついでにイノシシも。
人慣れしているようで一定の距離を保って近づいては来ませんでした。

今回の目的は更に六甲山を登ることでは無いので、ここから下山。
保久良神社につく頃には明るくなっていました。
境内には社の周囲を取り囲むように列石が、寸断されているようではあるが多く見られる。


手前の石に線刻があるような気も。

大きめの磐座も。
金鳥山自体にはここ以外に巨石は無かったので、もっと山上か下から運んだとしか思えません。自然石利用では無いように思えます。
遺物も至る所から多数発掘されているらしいので、かなりな歴史と信仰があったようです。
やっぱり街は違うなと感心。
田舎の磐座では磐座の下部からしか何も見つかりません。
ちなみに保久良神社の標高は200メートル程度、またしても200メートルです。
岡山鬼ノ城、屋島の城等と同じ、200メートルラインに巨石。
偶然では無い、はず。
地元の人以外でし知っているのは 、六甲山を登る人か、カタカムナ文字に興味のあるマニアくらいでしょう。
その昔この神社のある金鳥山山中で楢崎皐月が平十字なる人物よりのカタカムナ文字の巻物を見せられたという 。ただそのカタカムナ文字は、保久良神社とは直接の関係は無いようで、神社の記述にはどこにも見られない。
そもそも真偽すら明らかでない文字なので、本当に金鳥山で見せられたのかも怪しい。平十字という名前も金鳥山西側にある十文字山からとってるんじゃないかとも思われる。
私はカタカムナ自体を疑っているのではなくて、その場所を楢崎氏がぼかしているんじゃないのかと思っている。
以前読んだ本では、「池の周りに調査のために張ったワイヤーが動物の生活に影響を与えていると言って、平十字と名乗る猟師がクレームをつけてきて云々」と書かれていたと記憶しているが、金鳥山には池が見当たらないのである。
どこか別の山で起こった出来事を金鳥山に置き換えている、もしくは近辺の山の総称として金鳥山といったのかもしれない。
それはともかく、この保久良神社、磐座の宝庫である。
今回、高松深夜1時発のフェリーで神戸に5時過ぎに着き、そのまま保久良神社へ向かったので到着時、真っ暗である。
この時間に金鳥山を登るのは無謀かもしれないと思いつつ、近くのコインパーキングに車を停め、保久良神社に向かう。
神社に近付くにつれ、5時半だというのに何人もの人とすれ違ったり、追い越したりする。
境内に着くとこの時間のこんぴらさんではまず見られないほどの人が参拝している。
ただ、拝殿の前以外は暗くて何も見えないので、参拝だけすませて登山道へ向かう。
ただ、初めての場所なので、道の分岐点が見えないし、わからない。
他の人達が歩いて行く方へついて行くと、登山道の道標があった。
念のためにと持ってきていたヘッドランプと光量の強い懐中電灯を頼りに、出発。
大阪湾の夜景がきれいです。
さすがに大部分の人は参拝だけで、登山道にはほとんどいない。
ライトの灯りと自分の足音以外何もきこえない暗闇の中で、突然物音が、イノシシかと思いきや、他の登山者の足音。
他にも登っている人がいてひと安心、結局往復で20人以上に会いました。
田舎では昼間でもそんなに多くの人に会うことは無いので、びっくりです。
で、金鳥山の登山道にはほとんど石らしいものがなかったので、さらに進んで風吹岩という見晴らしのいいところへ。
ほとんどの石が切ったように角があり、単に風化して地上に現れたものでは無いような気もするが、今のところ特に祭祀していたとかという情報は聞いたことが無い。

メンヒルか磐座だと思うんですが。
猫がいました。ついでにイノシシも。
人慣れしているようで一定の距離を保って近づいては来ませんでした。
今回の目的は更に六甲山を登ることでは無いので、ここから下山。
保久良神社につく頃には明るくなっていました。
境内には社の周囲を取り囲むように列石が、寸断されているようではあるが多く見られる。
手前の石に線刻があるような気も。
大きめの磐座も。
金鳥山自体にはここ以外に巨石は無かったので、もっと山上か下から運んだとしか思えません。自然石利用では無いように思えます。
遺物も至る所から多数発掘されているらしいので、かなりな歴史と信仰があったようです。
やっぱり街は違うなと感心。
田舎の磐座では磐座の下部からしか何も見つかりません。
ちなみに保久良神社の標高は200メートル程度、またしても200メートルです。
岡山鬼ノ城、屋島の城等と同じ、200メートルラインに巨石。
偶然では無い、はず。