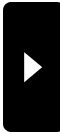2014年01月14日
Posted by こち at
2014年01月14日00:51 Comment(0)
滝山竜王社
遅ればせながら、あけましておめでとうございます。
うちは旧正月の方が本番なので、あんまり実感はありませんが。
正月休みはずっとヴェスパの修理に明け暮れてました。

前回行った立石山ですが、後日再訪してきました。
先ず、国道377号線にある道標から入っていきます。
ここまでは、前回と同じ。
先日の駐車場には行かず、その手前にあるもう一つの登山道入り口から登ります。
道路から少し入ったところにこんな看板があるのですが、初めてだと見落としそうになります。

ミカン山のイノシシ除け電撃柵を越えて、山へ入ります。

数分で簡易トイレ。

なぜ中国語?台湾土産のステッカーでも貼ったのだろうか?
このトイレを曲がると突然、石組の崩壊した参道が現れます。

すぐに山の名前の由来であろう竜王社の立石が現れますが、この山は滝山、続きの峰の最高峰が立石山。

高さ3m程度。
横、後ろ、崖の途中にも一回り小さな石が配置されています。
手水ももともとあった石をくりぬいているようです。

後にも巨石、もともとは並んでいたのが崩れたようです。

この竜王社、登り始めて10分で着いちゃいます。
滝山、立石山ともに頂上は430m程度、そんなに高くはないんだから、頂上に神社があってもよさそうモノです。
では、なぜ頂上ではなく、中途半端なところにあるのか?
私は海抜にあり、とみています。
実は、この竜王社、標高250m~300m位のところに鎮座しています。
屋島、鬼ノ城などの古代山城とされる遺物が大体250m強の場所に存在することから導き出したわたくしの勝手な説の通り、ここも超古代海岸線であったからに他なりません。
当時、ここは海辺で頂上は200m近い高さ、巨石は持ち上がらないので、前回見た通り頂上付近の峰々には小さな石で囲った磐境があるのみ。
また、竜王社の石の形、海岸で浸食されて丸くなった石が風化したように見えます。
以上の理由により、ここも超古代瀬戸内海岸ネットワークの通信基地であったとの結論に至るのであります。
毎度、私の妄想にお付き合いいただきありがとうございます。
本年も変わらず(性格は変わっているとよく言われる)、巨石探索に邁進いたしますので、大きな心で見守ってやってください。
より大きな地図で 磐座 を表示
うちは旧正月の方が本番なので、あんまり実感はありませんが。
正月休みはずっとヴェスパの修理に明け暮れてました。
前回行った立石山ですが、後日再訪してきました。
先ず、国道377号線にある道標から入っていきます。
ここまでは、前回と同じ。
先日の駐車場には行かず、その手前にあるもう一つの登山道入り口から登ります。
道路から少し入ったところにこんな看板があるのですが、初めてだと見落としそうになります。
ミカン山のイノシシ除け電撃柵を越えて、山へ入ります。
数分で簡易トイレ。

なぜ中国語?台湾土産のステッカーでも貼ったのだろうか?
このトイレを曲がると突然、石組の崩壊した参道が現れます。
すぐに山の名前の由来であろう竜王社の立石が現れますが、この山は滝山、続きの峰の最高峰が立石山。
高さ3m程度。
横、後ろ、崖の途中にも一回り小さな石が配置されています。
手水ももともとあった石をくりぬいているようです。
後にも巨石、もともとは並んでいたのが崩れたようです。
この竜王社、登り始めて10分で着いちゃいます。
滝山、立石山ともに頂上は430m程度、そんなに高くはないんだから、頂上に神社があってもよさそうモノです。
では、なぜ頂上ではなく、中途半端なところにあるのか?
私は海抜にあり、とみています。
実は、この竜王社、標高250m~300m位のところに鎮座しています。
屋島、鬼ノ城などの古代山城とされる遺物が大体250m強の場所に存在することから導き出したわたくしの勝手な説の通り、ここも超古代海岸線であったからに他なりません。
当時、ここは海辺で頂上は200m近い高さ、巨石は持ち上がらないので、前回見た通り頂上付近の峰々には小さな石で囲った磐境があるのみ。
また、竜王社の石の形、海岸で浸食されて丸くなった石が風化したように見えます。
以上の理由により、ここも超古代瀬戸内海岸ネットワークの通信基地であったとの結論に至るのであります。
毎度、私の妄想にお付き合いいただきありがとうございます。
本年も変わらず(性格は変わっているとよく言われる)、巨石探索に邁進いたしますので、大きな心で見守ってやってください。
より大きな地図で 磐座 を表示