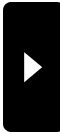2013年11月17日
Posted by こち at
2013年11月17日01:29 Comment(0)
屋島北嶺
屋島北嶺を北端の長崎の鼻側の登山道より登ってきました。

登り始めてすぐに、石切り場の跡と言われている洞窟が見えてきます。
きれいにノミ跡が残るこの洞窟ですが、隣の庵治では山ごと崩す勢いで露天掘りをしているのに、ここは洞窟状に坑道を穿っています。

現在、崩落の危険があるため立ち入り禁止ですが、前回登った10年前は奥まで入れました。
最長120mあるこの洞窟、本当に単なる石切り場なのでしょうか?

長崎の鼻には江戸末期の砲台跡が残っているので、その弾薬庫に利用したのか?それとも金か何かを採掘しようと掘ったのか?
資料がないのでよくわかりません。
さらに登っていくと、岩場に出ます。
独特の形状の岩ですが、ここが海抜200m付近。

前回妄想したように、海進期この高さの位置が波打ち際であった証拠である。
屋島城の城門と言われる遺構もこの高さである。
北嶺南部の斜面にある石切り場跡と言われる洞窟もこの高さである。
等高線の密なこんな急斜面で切り出した石をどうやって麓へおろしたのか、もしくは山頂へ上げたのか?
無理です。これもここが波打ち際であった証拠である。
妄想はそこまでにして、登山を続けましょう。
と思ったら、間もなく遊鶴亭に到着。
ここからは山頂の平らな遊歩道が北嶺を囲むように東西両側に延び、北嶺南端で合流しています。
舗装された遊歩道を歩くのは面白くないと、よく見ると真ん中に尾根筋の土の道が。

迷わずここを進みます。
しばらく進むと千間堂跡と言われる礎石跡に着きます。ここが鑑真和尚が建てたといわれる最初の屋島寺であったらしい。
どの資料を見ても「たぶん」としか書いていませんが・・・。
ほどなくすると、北嶺の南端の芝生の広場に出ます。
ここからまた、中央部に尾根伝いの道があるので、そちらを進みます。
この道、なんと石畳がしいてあります。草や土の中に埋もれている所も多いのですが、ずっと続いています。

列石です。

しばらく行くと、本当に尾根の先端を歩く道に変わり、あきらかに人工物の立石、列石、階段、江戸時代以降に彫られたであろう漢数字。

途中、割れてしまった鏡岩もありました。
真東に向いています。
尾根筋を迂回するように作られた遊歩道は、つい最近のもので、本来はこちらがメインの道であったようです。
この漢数字、確認できたものは二つですが、北側から「四七」、「五三」なので、道標かなにかでは?
ところどころ石が割れて崩れてきているので、場所によっては迂回しなければいけませんが、基本的にはこの道は生きています。
県の方でも、この辺りは「階段状遺構」と指定されているようですが、特別な保護はされていないようです。

北嶺と南嶺の中間点にある254mの小峰、ここに列石、立石、階段遺構があります。
ここを抜けるとすぐに南嶺の談古嶺に到着します。
以上、北嶺は今は何も無く寂れているものの、古代より江戸時代までは、人が頻繁に入っていたものとみられます。
再度実地調査をしてみて、海抜200m付近が巨石文明の時代の海岸線であったことを確認できた有意義な一日でした。
ここで日が暮れかけたので、今日はおしまい。元来た道を、たった40分で急ぎ足で逃げ帰りました。

登り始めてすぐに、石切り場の跡と言われている洞窟が見えてきます。
きれいにノミ跡が残るこの洞窟ですが、隣の庵治では山ごと崩す勢いで露天掘りをしているのに、ここは洞窟状に坑道を穿っています。

現在、崩落の危険があるため立ち入り禁止ですが、前回登った10年前は奥まで入れました。
最長120mあるこの洞窟、本当に単なる石切り場なのでしょうか?

長崎の鼻には江戸末期の砲台跡が残っているので、その弾薬庫に利用したのか?それとも金か何かを採掘しようと掘ったのか?
資料がないのでよくわかりません。
さらに登っていくと、岩場に出ます。
独特の形状の岩ですが、ここが海抜200m付近。

前回妄想したように、海進期この高さの位置が波打ち際であった証拠である。
屋島城の城門と言われる遺構もこの高さである。
北嶺南部の斜面にある石切り場跡と言われる洞窟もこの高さである。
等高線の密なこんな急斜面で切り出した石をどうやって麓へおろしたのか、もしくは山頂へ上げたのか?
無理です。これもここが波打ち際であった証拠である。
妄想はそこまでにして、登山を続けましょう。
と思ったら、間もなく遊鶴亭に到着。
ここからは山頂の平らな遊歩道が北嶺を囲むように東西両側に延び、北嶺南端で合流しています。
舗装された遊歩道を歩くのは面白くないと、よく見ると真ん中に尾根筋の土の道が。

迷わずここを進みます。
しばらく進むと千間堂跡と言われる礎石跡に着きます。ここが鑑真和尚が建てたといわれる最初の屋島寺であったらしい。
どの資料を見ても「たぶん」としか書いていませんが・・・。
ほどなくすると、北嶺の南端の芝生の広場に出ます。
ここからまた、中央部に尾根伝いの道があるので、そちらを進みます。
この道、なんと石畳がしいてあります。草や土の中に埋もれている所も多いのですが、ずっと続いています。

列石です。

しばらく行くと、本当に尾根の先端を歩く道に変わり、あきらかに人工物の立石、列石、階段、江戸時代以降に彫られたであろう漢数字。

途中、割れてしまった鏡岩もありました。
真東に向いています。
尾根筋を迂回するように作られた遊歩道は、つい最近のもので、本来はこちらがメインの道であったようです。
この漢数字、確認できたものは二つですが、北側から「四七」、「五三」なので、道標かなにかでは?
ところどころ石が割れて崩れてきているので、場所によっては迂回しなければいけませんが、基本的にはこの道は生きています。
県の方でも、この辺りは「階段状遺構」と指定されているようですが、特別な保護はされていないようです。

北嶺と南嶺の中間点にある254mの小峰、ここに列石、立石、階段遺構があります。
ここを抜けるとすぐに南嶺の談古嶺に到着します。
以上、北嶺は今は何も無く寂れているものの、古代より江戸時代までは、人が頻繁に入っていたものとみられます。
再度実地調査をしてみて、海抜200m付近が巨石文明の時代の海岸線であったことを確認できた有意義な一日でした。
ここで日が暮れかけたので、今日はおしまい。元来た道を、たった40分で急ぎ足で逃げ帰りました。